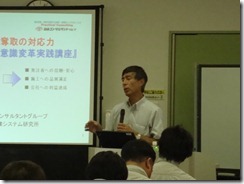いわけんブログ
ふれあい事業 in 煙山小学校
2012年8月28日 11:58盛岡支部
経営革新講座「現場代理人の意識変革実践講座」を開催しました。
2012年8月27日 19:16岩手県建設業協会
一戸まつり
2012年8月27日 16:24二戸支部
「のだまつり」が開催されました
2012年8月27日 16:11久慈支部
平成24年度建設業ふれあい事業IN大迫中学校
2012年8月20日 11:35花巻支部
市道清掃活動
2012年8月20日 11:10花巻支部
公共工事動向7月を更新しました。
2012年8月10日 18:55岩手県建設業協会
岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内7月版)を掲載しました。
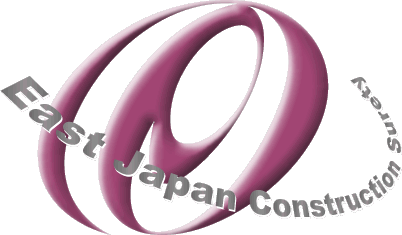
↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)7月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を「道の日」 「黄金ロードふれあい作戦」清掃活動実施
2012年8月10日 16:42一関支部
道路の意義、重要性に対する国民の関心と道路愛護の精神を高めることを目的に、8月10日の「道の日」に毎年清掃活動を実施しております。
一関支部青年部(宇部和彦会長)が中心となり、県南広域振興局一関土木センター、一関市、花泉支所、平泉町の各関係機関と当支部(佐々木一嘉支部長)会員と女性マネジングスタッフ協議会の総勢100名ほど参加。
①国道284号市道竹山東工業団地線、②主要地方道平泉厳美渓線、③一般国道342号(花泉方面)の3編成にて清掃
磐井川河川敷にて開会

県南広域振興局一関土木センター 高橋所長さまのご挨拶

今日も暑いね~・・・

②平泉(世界遺産登録)地区のゴミは、これだけでした。
地域の皆さんがきれいにしているのでしょうね。

閉会式での一関市建設部 菊池部長さまより講評

2012「道の日」イベント奉仕活動。
2012年8月10日 15:42千厩支部
北の道クリーンキャンペーンを開催
2012年8月10日 15:09二戸支部
8月8日(水) 毎年開催しております、二戸支部青年部主催のクリーンキャンペーン
を行いました。8月10日「道の日」にちなみ、二戸広域圏の道路をきれいにすることを目的」に開催し、今年で20回目(二十歳)を迎えました。
当初は、二戸振興局土木部(現 二戸土木センター)と一緒に道路のごみ・空き缶拾いを行っておりました。今は、国交省・振興局・市町村の職員が道路のごみ・空き缶拾いを行い、青年部は、街路樹の剪定や草刈りを行っております。
県道二戸一戸線の街路樹の剪定や草刈り(草取り)の作業風景。
街路樹剪定中
≪ごみの量≫
・剪定等の枝・草 2tダンプ2台
・道路で拾ったごみ・空き缶等 不燃ごみ100kg 可燃ごみ90kg
年々、量は減ってきているようですが、毎年、珍しいごみが混じって
います。 今回は、電気炊飯器が1台ありました。ごみは、決められた場所に捨てましょう!
沿岸被災地支援ボランティア活動
2012年8月10日 14:13北上支部
北上支部では、北上市建設業協会と合同で7月7日(土)3回目の被災地支援活動を釜石市で行いました。
釜石市唐丹町小白浜漁港付近です。
あいにくの雨でしたが、24社41人が参加しました。
地元の方(左)から釜石のボランティアセンターの方が作業内容を確認しました。
ボランティアセンターの方から作業内容の指示を受けています。
今回は、重機とダンプを持ち込んでガレキの撤去と草刈作業を行いました。
草刈後の状況です。1枚目の写真と比べてみてください。
撤去したガレキ等は、集積所に運んで分別処理します。
午後からは、鵜住居常楽寺で側溝の土砂を撤去しました。
写真後方に供養塔が倒れています。1年たってもまだ直せないでいます。
私たちのほかにもバスで200人以上のボランティアの方が訪れていました。
まだまだ復興には時間がかかりそうです。
道の日in宮古(道路クリーン作戦・街頭パレード)
2012年8月10日 12:26宮古支部
北上支部青年部「建設業ふれあい事業」
2012年8月 9日 11:57北上支部
建退共岩手県支部 ☆ お知らせ ☆
2012年8月 8日 08:13建退共岩手県支部
グラフけんたいきょうー岩手県支部ー
(平成19年度~平成23年度)直近5年間の建退共岩手県支部の事業概況をグラフにしてみました。
加入事業所(共済契約者)、手帳所持者(被共済者)、掛金収納額は、
平成23年度において東日本大震災の被災地に対する特例措置が実施
されたこと、復旧、復興工事の発注が始まったことが反映されています。なお、被共済者加入率は、分母になるデータが平成22年度から置き
換わったことも加入率アップの一因となっています。詳しくは こちら をクリックして御覧下さい。
お 知 ら せ 建退共岩手県支部では、平成24年8月13日から8月16日まで
お休みをいただきます。
一般社団法人岩手県建設業協会・同関連団体は、全て同様と
なりますのでご了承下さい。
遠野支部「かっぱ工事隊」夢明り
2012年8月 3日 13:28遠野支部
前夜祭プレイベントが21日開催された
夜のとばりがおりるころ、2000個の灯籠に灯りがともされました。
工事隊も衣替えです。よく見ると建設業協会青年部となっております。その工事隊も点灯し、灯りが少しずつ明るさを増すころには幻想的で夏の風物詩のように様変わりします。



遠野市内の保育園や小学校の児童がそれぞれに、復興への思い、願いなどが書かれておりました。
会場を訪れた、子供たちも親子で自分が書いたのを探しておりました。
灯籠の明りが北ウイングを想わせる滑走路のようでした。

さっそく委員長の挨拶から始まりました。 
会場には団子屋さんも来ておりました

プレイベントでは、地域の黒渕さんの昔話と、市内の伊禮さんのバイオリンによる演奏が行われ、美しい音色に酔いしれておりました。
またアンコールも望まれそれなりに応えてくれました。前夜祭も予定の時間が過ぎても盛りあがっておりました。
これまでの「かっぱ工事隊」の活動
今までの活動が8月6日のIBC岩手放送でTV放映されます。
標題は岩手希望の一歩 「復興の味方かっぱ工事隊」 沿岸の復旧・復興を支える人々
遠野支部「遠野かっぱ工事隊」の活動その2
2012年8月 3日 13:11遠野支部
7月21日 開通に先駆けかっぱロードフェステバルが開催された。
フェステバルに向けてかっぱ工事隊がたむろしております。橋の上から、魚を狙っているのか、好物のキュウリが流れて来るのか川面を見ています。

ここがかっぱ淵の近くだよ。 

上の高所作業車は高さが20mまで上がります。今回のフェステバルのため千葉県から搬入されました。荷台は10名まで乗れます。右の写真はかっぱ副隊長と隊員です。小生もさそく搭乗しました。乗れば高い!左の写真が かっぱ淵から「清め水」を汲みあげシンボルモニュメントまででバケツリレーを行いました。 (300人)
早々と、農家の産直売店の準備です。

シャトルバスからこっそり降りてきたのは、岩手建設工業新聞社の折目記者でした。カメラ持参ですからBGですね。オレンジ色が鮮やかです。何と遠野合同庁舎、県OBの皆様方もイベント一役です。


間もなくオープニングセレモニーです。
この企画は、土渕町地域づくり連絡協議会・土渕町町づくりを考える会・遠野市・岩手県県南広域振興局・岩手県建設業協会遠野支部・遠野市観光協会・遠野商工会・遠野ふるさと公社・他です。参加者から見て町おこしの感がありました。

司会進行はご当地かっぱじいの運万春男さんでスタートで行われました。 

委員長菊池盛治様 遠野市長本田敏秋様 

遠野土木センター所長藤本栄二様
岩手県議会議員 工藤勝子様 
遠野市議 議長 新田勝見様です。

最初に郷土芸能パレードとして宮古市から参加され、景気よく宮古市の山口太鼓で始まりました。
かっぱモニュメント除幕式です。可愛いです。これから、土渕町で交差点で交通事故の無いように見守っていてくれると思っております。

黄色いバケツに「清水」が入っております。親子で手渡しです。

参加者300人でモニュメントまで「清水」と、ご供物をバケツリレーしました。最後は、参加者みんなで手をつなぎ絆を確かめました。
高さ20mの高所作業車からTV放映です。
モニュメント会場へ移動です。建設機械の乗車体験です。人気です


舞台から市議会議員餅まきです。最初に子供たちからスタートし、その後は一般でした。見ていますと、下を見ていた人がいっぱい拾っていました。 そのほかつきたての餅も会場で振る舞われました。
かっぱ工事隊のトークショウです。右の写真ゆるキャラふれあいです。



子供たちの道路のお絵書きです。舞台のほうではまだまだ郷土芸能が続いています。 予定時間を終えてもまだ賑やかでした。盛会理に終えたと思っております。県、市職員他関係団体はもとより、地域住民の皆様方のパワーあふれる活動には敬意を表するものであります。
次は、かっぱ工事隊「夢明り」を掲載します。
遠野支部かっぱ工事隊の活動(その1)
2012年7月30日 16:20遠野支部
まず最初に 「遠野かっぱ工事隊」の誕生でした。
昨年度、東日本大震災が発生いたしました。その1年後、3月12日、山肌には残雪があるころ眠から目覚めました。この道路は復興道路として遠野市から北に向かい、震災地への物流等の道路として、宮古市、岩泉、軽米町方面に通じております。
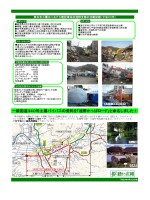
「遠野かっぱ工事隊」は、遠野の土渕で生まれたかっぱが、地域のために、道や川の工事を行うがんばる工事隊である。ついで、震災が発生したときには、人道支援・復旧・復興と工事隊員の家族など皆で支援し、遠野のかっぱ工事隊員が復興への道筋の一躍を担って来ました。
あの日あのときの3月11日発生し、その次の日より被災地の道路開設を行いました。その当時の作業状況の写真が遠野風の丘道の駅に展示しております。
「遠野かっぱ工事隊」は、 被災地とは古来より塩の道で親戚も多数あり、とても他人ごとではありませんでした。月日が経過しし、だいぶ元気を取り戻しておりますが、いまでも震災に負けないよう、永遠のふるさと遠野の元気と被災された沿岸地域が、みんな元気な姿にもどれるよう願って活動しております。
「遠野野かっぱ工事隊」は、遠野市内の国道340号土渕バイパスが一部供用の開始となり、その前にPRキャラバン隊として活動に出かけることとなりました。
6月15日
岩手県建設業協会遠野支部出発ー遠野テレビ-遠野市役所ー遠野市観光協会ーFM岩手遠野支局―道の駅風の丘
いよいよ出発です。かりんちゃんも準備中です。かっぱはなんて泣くんだろうといいながらスタンバイです。遠野土木センターからは及川さんのほか数名の参加で出発いたしました

佐々木隊長がとおのテレビ訪問です。かっぱ語でPRでしょうか?
遠野市内に一斉に放映されました。CM付でした。

遠野駅前でのPRです。近くにいたおじさんも興味ありそうでした。
6月18日 岩手県建設業協会宮古支部ー宮古市役所ー山田町役場―大槌町役場

今日は宮古だ!佐々木隊長に変わり織笠副隊長です。今日も県行政の及川様にも同伴していただき小生も参加させていただきました。

宮古支部で大坂支部長様と松舘事務長様が迎えて戴きました。 
さあー宮古だ。宮古市役所に入ります 
市長室です。議会中でお会いできませんでした。 
大坂支部長様のご配慮で宮古市都市整備部にお邪魔し、国道340号の一部供用開始と産業振興の道路の重要性と観光資源の活用等について広報活動いたしました。 
宮古市都市整備部にはいり遠野かっぱ工事隊のPRをさせていただきました。 
宮古市都市整備部の皆様が総立ちで歓迎して戴きました。 
ここは、FM宮古です。放送時間までスタンバイ。放送開始です。シ―シ―静かにして下さい。 
宮古市総合福祉センターにもお邪魔しました。かっぱのかりんちゃんはどこ ! 

山田町役場へもお伺いしました。山田町の保育園から要請を受け、役場どなりの保育園にも出かけました。

大槌町SCマストでPRでした。おおつちさいがいエフエムにもおじゃまして放送もお願いしてきました。
6月19日 岩手県建設業協会釜石支部ー釜石市役所ー陸全高田市役所ー大船渡市役所

釜石市長がお出迎えしてくれました。

その足で陸前高田市にでかけました。

陸前高田市長にもお出迎えいただき、今回の訪問についてPRを兼ね説明をしてきました。

続いて大船渡市役所です。皆で歓迎してくれました。

見たことのある人がおりました。大船渡市都市整備部部長さまです。震災を思い出します。遠野土木センターに在籍しているとき赤松課長。あの時(3月11日)は一生懸命でご活躍でした。

その足で、大船渡市の社会福祉協議会へも訪問しPRしました。
6月21日 岩手県庁ー岩手日報ーテレビ岩手ーFM岩手本社―岩手放送ー岩手朝日テレビ―岩手めんこいテレビ

岩手県知事に訪問しました。建設業の復旧、復興の支援とこの度の遠野地域の、観光資源のPRなどの活動の報告をいたしました。
今回の訪問では、震災地の早急な復旧、復興をお祈り致しますとともに、各支部の支部長、事務長、青年部長様のご配慮を賜りまして、厚くお礼申し上げます。 絆
この後、かっぱロードフェステバルの紹介です。
釜石警察署いよいよ解体
2012年7月25日 15:53釜石支部
遠野支部 復興道路一部供用開始
2012年7月24日 17:12遠野支部
7月22日遠野かっぱロード(国道340号土渕バイパス)が一部供用の開始となった。
式典では、遠野土木センター所長の挨拶と来賓として本田市長、工藤県議のご祝辞がありました。その他、県土整備部道路建設課の高橋課長、遠野市議会議員の多数のご参加と工事関係者、地元協力会、地域住民の皆様方でテープカットをして開通を祝いました。
いよいよ式典です。主催者、来賓、県議会議員、市議会議員、地元地域づくり連絡協議会、遠野市、岩手県県南広域振興局、かっぱ工事隊などの皆様がお席に付いております。

主催者として、県南広域振興局土木部遠野土木センター所長藤本栄二様は、東日本大震災の際に国道340号は、復興支援道路として大いに活用されました。この路線は復興支援道路として位置ずけられ、国道340号線の整備は本県の復興を力強くけん引するものとし、引き続き立丸峠の全面改良にも早期の事業着手 を目指したいと挨拶されました。

遠野市長本田敏秋様より祝辞を戴きました。

地元、工藤勝子県議会議員の祝辞を戴きました。

開通を祝し、テープカットが行われ、最後は、主席者全員で万歳三唱して開通を祝いました。

パレードを前に、関係者とかっぱ工事隊と記念撮影を行いました。

パトロールカーを先導に関係車両が列をなしパレードです。かっぱ工事隊が手をふって送ります。

かっぱ工事隊は、休む間もなくテレビ局,新聞社などのインタビューに応えておりました。 かっぱ工事隊の活動経過は次に続く。
建設業景況調査(東日本大震災 被災地版)6月調査
2012年7月23日 10:21岩手県建設業協会
岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(東日本大震災 被災地版)6月調査(平成24年度第1回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。
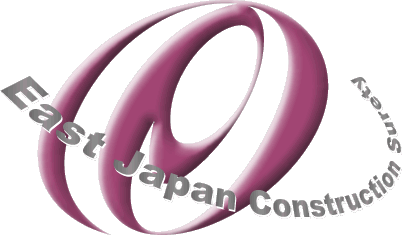
↓PDFファイル↓
建設業景況調査(岩手県版)6月調査
調査結果(概要) → こちら(PDF)
データ表 → こちら(PDF)
建設業景況調査(東日本大震災被災地版)6月調査
調査結果(概要) → こちら(PDF)
月別アーカイブ
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年


![clip_image002[4] clip_image002[4]](https://www.iwaken.or.jp/info/Windows-Live-Writer/99715e24097c_A3EB/clip_image002%5B4%5D_thumb.jpg)
![clip_image002[6] clip_image002[6]](https://www.iwaken.or.jp/info/Windows-Live-Writer/99715e24097c_A3EB/clip_image002%5B6%5D_thumb.jpg)