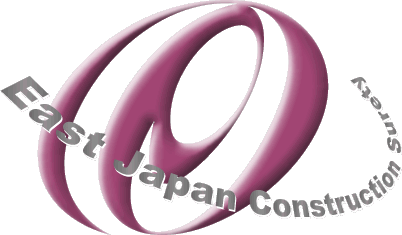いわけんブログ
- 岩手県建設業協会 一覧
公共工事動向8月を更新しました
2011年9月 5日 13:16岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内8月版)を掲載しました。↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)8月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
平成23年度 第4回経営革新講座の開催案内
2011年8月 4日 19:01岩手県建設業協会
今年度第4回となる経営革新講座は、コストダウン、社員育成をテーマに『強い会社にするための経営の極意』と『社長の元気が会社を救う~コミュニケーションで会社は元気に生まれかわる~』の2部構成で開催いたします。
本講座の第1部では関口清講師から、経営者が自分の経営哲学を持ち、自社の発展に限りない情熱を傾けてきた会社を「強い会社にする」ための方策とはなにか、経営者と語り合った経験を生かして、解説いただきます。
また、第2部では新田祥子講師から、経営者がプラス思考を持ち、「元気力」をコミュニケーションにより、社内に伝搬させ、活性化するための方法を実演やロールプレイングを交えて解説いただきます。
下記日程で開催いたしますので、ぜひこの機会にご参加くださいますようご案内いたします。
日時:平成23年8月23日(火)13:30~16:40
場所:建設研修センター
講師:(株)建設経営サービス 提携講師 関口 清 氏
(株)建設経営サービス 提携講師 新田 祥子 氏
案内・申込書は・・・・「こちら」公共工事動向7月を更新しました
2011年8月 4日 11:53岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内7月版)を掲載しました。↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)7月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
建設業景況調査(東日本大震災 被災地版)6月調査
2011年7月21日 14:19岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(東日本大震災 被災地版)6月調査(平成23年度第1回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。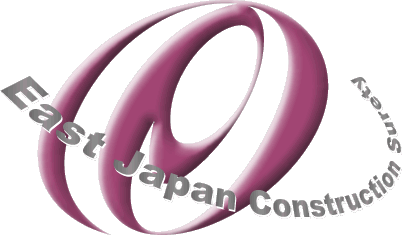
↓PDFファイル↓
↓PDFファイル↓
建設業景況調査(岩手県版)6月調査
調査結果(概要) → こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
建設業景況調査(岩手県版)3月調査・6月調査
2011年7月21日 13:55岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(岩手県版)の3月調査(平成22年度第4回)・6月調査(平成23年度第1回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。↓PDFファイル↓
↓PDFファイル↓
建設業景況調査(岩手県版)6月調査
調査結果(概要) → こちら(PDF)
データ表 → こちら(PDF)
建設業景況調査(岩手県版)3月調査
調査結果(概要) → こちら(PDF)
データ表 → こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
平成23年度経営革新講座《第3回開催します》
2011年7月 7日 17:20岩手県建設業協会
岩手県建設業協会では岩手県と共催で第3回目となる経営革新講座を開催いたします。
今回は株式会社建設経営サービスから講師をお迎えし、経営管理・利益創出をテーマに『中小建設企業における自社分析のポイントと経営再構築への考察~建設業経営の将来方向の早期決断~』を講義いたします。
また、併せて雇用・能力開発機構から助成金の制度説明をいたします。
詳細につきましては案内・申込書「こちら」をご覧ください。
ぜひこの機会にご参加くださいますようご案内いたします。
1 日 時 平成23年7月29日(金)13:30~15:30
2 場 所 建設研修センター2階 第1研修室
3 案内・申込書 ⇒ こ ち ら公共工事動向6月を更新しました
2011年7月 6日 08:51岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内6月版)を掲載しました。
↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)6月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
第1回経営革新講座「その時建設企業は何をなすべきか~阪神・淡路大震災に学ぶ~」を開催しました
2011年6月14日 11:16岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会では、岩手県との共催、(社)岩手県建設産業団体連合会、(財)いわて産業振興センター後援のもと、第1回経営革新講座「その時建設企業は何をなすべきか~阪神・淡路大震災に学ぶ~」を6月9日(木)あえりあ遠野・10日(金)宮古市総合体育館にて開催しました。
講師は兵庫県より兵庫県職員1名・建設企業5名を迎え、阪神・大震災時において兵庫県の建設企業がどう対応し復旧に向き合ったかを説明しました。
兵庫県は阪神・淡路大震災でのインフラの復旧・復興について、当時の被害状況を解説したうえで、災害復旧工事、復興に係るまちづくりなどを説明し、建設企業は阪神・淡路大震災当時の復旧・復興活動の各社記録していた実際に経験したことを説明しました。
各建設企業は、当時はまず復旧ということが大事ではあったが、10年以上かかる建設工事を2、3年で実施した結果、地元の建設工事が急激に減少している現状になっている。
このことから、岩手県においても同様のことが想定されるため、要員確保の必要性と数年後に現在の体制を継続できないことを想定しての事業計画を立てることが必要ではないかと述べました。
また、ある建設企業は復旧・復興の面からいずれは大量に住宅を建てる必要性が出てくるため、住宅部門に進出し、充分な実績を得られたことを話しました。
今回の講座において参加された建設企業は参考になる情報を得られたかと思われます。
公共工事動向5月を更新しました
2011年6月 9日 10:53岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内5月版)を掲載しました。
↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)5月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
平成23年度電子納品研修会開催について
2011年6月 7日 13:12岩手県建設業協会
岩手県建設業協会では円滑に電子納品への移行ができるよう、下記により研修会を開催することといたしました。
詳細につきましては開催案内・申込書をご覧ください。
ぜひこの機会にご参加くださいますようご案内いたします。
開 催 日 7月 5日(火)~7月22日(金)
時 間 10:00~16:00
場 所 (財)岩手県土木技術振興協会内 CALS/ECセンター
内 容 電子納品総合講習、CAD講習(ソフト名:デキスパート、上出来、武蔵)
受 講 料 1人 2,000円(税込)
対 象 (社)岩手県建設業協会会員、(社)岩手県建設産業団体連合会会員団体の会員企業
申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、平成23年6月17日(金)までに社団法人岩手県建設業協会へFAXにてお申込みお願いいたします。
開催案内・申込書 → こちら請負資格者名簿を発刊いたします
2011年5月30日 14:37岩手県建設業協会
平成23・24年度県営建設工事請負資格者名簿につきまして、本年度定期発刊として岩手県土整備部長の監修のもと、当協会で一般頒布することとなりました。
つきましては下記により取りまとめいたしますので、ご希望の方は直接必要事項等ご記入のうえお申し込み下さい。
図書名:平成23・24年度県営建設工事請負資格者名簿
価 格:未定(参考平成21・22年度名簿 印刷部数550冊 @2,500円)
申 込:会社名・住所・電話番号・希望冊数・担当者名等を任意の書式でFAXにて申込
申込照会先:社団法人岩手県建設業協会 TEL019-653-6111
FAX019-625-1792
発 刊:6月中旬から下旬を予定平成23年度社団法人岩手県建設業協会定時総会開催
2011年5月26日 10:18岩手県建設業協会
平成23年5月24日(火)に平成23年度社団法人岩手県建設業協会定時総会を建設研修センターで開催しました。
総会では平成23年度の事業計画として、震災対応およびコンプライアンスに関する活動および防災体制の強化に重点をおくとともに、一般社団法人認可を目指し、公益事業に取り組むことを決定しました。
そのほか、議案審議に先立って行われた建設業協会会長表彰等の表彰式において、協会員など83名の方々が岩手県建設業協会表彰など栄誉ある表彰を受賞されました。平成23年度事業計画(抜粋) → こちら

平成23年度定時総会

会長あいさつ

受賞者一同
建設業協会表彰 51名(社)
全建表彰 20名(社)
全国技士会表彰 6名
福祉共済団表彰 6名
「東日本大震災への取組」を掲載しました。
2011年5月23日 11:42岩手県建設業協会
平成23年度第1回経営革新講座開催のお知らせ
2011年5月18日 15:59岩手県建設業協会
今回の東日本大震災の被災を踏まえ、建設企業が地域の基盤づくりに貢献する企業として、「ヒト・モノ・カネ・ジョウホウ」に代表される経営資源・資機材の調達・確保を進め、さらに、行政機関との連携のもと、どのように復旧・復興に携わるべきかについて、短期・中長期の経営計画の立て方を中心とした講座「その時建設企業は何をなすべきか~阪神・淡路大震災に学ぶ~」を次のとおり開催いたします。
本講座では、平成7年の阪神・淡路大震災時における兵庫県職員、兵庫県神戸市の建設企業の実際の経験に基づいた震災時の対応を解説いただきます。
つきましては、ぜひ御参加くださいますよう御案内申し上げます。日時・場所・講師
6月 9日(木) 13:00~15:30 あえりあ遠野
「震災時の建設企業の役割~その時建設企業は何をなすべきか~(仮題)」
講師 山田 俊治氏 (株)山田工務店 取締役社長(神戸市中央区)
講師 中島 俊一氏 (株)明和工務店 代表取締役(神戸市中央区)
「阪神・淡路大震災における土木インフラの復興について」
講師 宮本 眞介氏 兵庫県県土整備部県土企画局技術企画課長
6月10日(金) 13:00~15:30 宮古市民総合体育館 シーアリーナ
「震災時の建設企業の役割~その時建設企業は何をなすべきか~(仮題)」
講師 平岡 勝功氏 関西建設工業(株) 代表取締役(神戸市西区)
講師 今津 由雄氏 今津建設(株) 取締役社長(神戸市兵庫区)
講師 北浦 督通氏 北浦建設(株) 代表取締役社長(神戸市兵庫区)
「阪神・淡路大震災における土木インフラの復興について」
講師 宮本 眞介氏 兵庫県県土整備部県土企画局技術企画課長対 象 岩手県内に事業所を持つ建設業許可業者・行政職員
主 催 岩手県・(社)岩手県建設業協会経営支援センター
後 援 (財)いわて産業振興センター・(社)岩手県建設産業団体連合会
申 込 先 添付申込書に必要事項を御記入の上、岩手県建設業協会あてにお申込みください。
案内申込書 → こちら
岩手県建設業協会ホームページでは東日本大震災に関する取り組み等の記事をいわけんブログにて掲載しておりますので、どうぞご覧ください。東日本大震災~発生当初の取組み~
2011年5月11日 19:00岩手県建設業協会
この度の震災にあたり、全国の皆様から多大なるご支援を頂きましたことに対し衷心より感謝申し上げます。皆さまからのご支援に恥じぬよう、我々は故郷の希望を取り戻すため復興に向けた作業に取り組んでおります。
社団法人岩手県建設業協会長メッセージ
このたびの大震災により犠牲となられた皆様に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された方々、そのご家族・関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を切に祈念いたします。
発災から2か月余りが過ぎましたが、岩手県三陸海岸を襲った大津波は、7,000人を超える犠牲者と行方不明者を出しております。未だに余震が止まない状況で、家をなくされ避難を余儀なくされておられる方も夥しい数に上ります。私ども建設業界におきましても、会員、その従業員などに多くの犠牲者を出しておりますし、会社社屋も流出するなど甚大な被害を蒙っております。
今現地におきましては、自衛隊・消防・警察を始め、国・県・市町村、関係団体などの方々により懸命な復旧作業や被災者への雇用対策など支援がなされており、建設業界におきましても、瓦礫の撤去や道路の応急工事など復旧に向けて日夜作業に努めているところでございます。
もとより、私ども建設業界は、県民の皆様の安心・安全・快適のために、県土の社会資本整備、災害対応の役割を担っており、このたびの復旧・復興には沿岸・内陸を問わず業界の総力を挙げて果敢に取り組んでおります。
これから復旧・復興までには、長い道のりになるものと考えられます。避難されております方々には今しばらく不自由な生活が続きますが、必ずや豊かで平穏な生活を取り戻すことができるものと信じております。
私ども建設業協会は、渾身の力を振り絞って我々の故郷であるいわてを一日も早く復興し、理想郷いわての実現にむけて県民の皆様とともに手を携え邁進して参りたいと存じます。平成23年5月11日
社団法人岩手県建設業協会
会長 宇部 貞宏
社団法人岩手県建設業協会の取組み
2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震は、日本の観測史上最大のマグニチュード9.0を記録しました。この地震により東北地方太平洋沿岸部は大津波に襲われ、壊滅的な被害をもたらしました。

(高さ10mの防潮堤を超える津波 宮古市田老)
被災者数(2011年5月10日現在 警視庁まとめ)
死者
14,949人(岩手県 4,400人)
行方不明者
9,880人(岩手県 3,275人)
避難
117,085人
当協会は地域の基幹産業としての社会的使命から、災害パトロール、応急復旧活動、ガレキ撤去作業、人道支援に災害発生当初より取り組んでおります。
動画「東日本大震災 復興の懸け橋」
- 3月11日
- (本部)災害対策本部設置(本部長:宇部会長)
(一関支部)国交省より三陸国道事務所大船渡出張所への派遣要請
(遠野支部)県遠野土木センターに対策本部が設置、会員企業へダンプ・ローダー・BHハサミ付などの建設機械の協力要請、応急復旧作業開始
- 3月12日
- (大船渡支部)大船渡市の指示で道路等のがれき撤去・応急復旧活動開始
(釜石支部)釜石・大槌地区災害対策本部設置(釜石地区合同庁舎内)、がれき・泥の撤去作業開始(沿岸広域振興局・釜石市・釜石支部)
_1.jpg)
.jpg)
_1.jpg)
_3.jpg)
_1.jpg)
(宮古支部)災害対応について県・宮古土木センターと打合
(岩泉支部)県岩泉土木センターと災害対策に係る打合
(久慈支部)県北広域振興局土木部と災害復旧等対策協議
(盛岡支部)今後の対応体制について協議
(一関支部)全会員支部集合各担当区域をパトロール、一関市・岩手県から応急復旧依頼、炊き出し実施(国交省一関出張所・一関土木センター)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(千厩支部)各社自主パトロール実施(11日から)、県千厩土木センターと応急復旧活動について連絡
(遠野支部)支援車両現場搬入、一部応急復旧活動実施(釜石合庁前・釜石遠野線・鵜住居交差点国道45号・大槌町国道45号)


- 3月13日
- (本部)会長・専務 岩手県・岩手河川国道事務所訪問
(大船渡支部)県大船渡土木センターの指示で道路等のがれき撤去・応急復旧活動開始
(宮古支部)建設業協会宮古支部災害対策本部を大坂建設に設置、自衛隊の後方支援として道路復旧・がれき撤去作業開始(田老・鍬ヶ崎・金浜・赤前地区)
(岩泉支部)国道等の幹線道路の通行確保のため廃車やがれき撤去作業開始
.jpg)
.jpg)
(久慈支部)久慈市役所土木課と今後の応急復旧について協議、各社復旧応急対応
.jpg)
.jpg)
(一関支部)国交省一関出張所からの指示で陸前高田市において国道45号線復旧作業開始
(千厩支部)県千厩土木センター経由で陸前高田への応援要請
(遠野支部)本格的支援活動実施、国土交通省管轄への支援要請、通行止看板設置・燃料供給について行政へ支援要請
- 3月14日
- (本部)緊急支部長会議(建設業協会としての復旧対応等の協議:全県を4ブロックに分け、沿岸支部を内陸支部が支援する体制を構築)
(大船渡支部)岩手県・大船渡市からの指示で応急復旧活動実施
(久慈支部)県北広域振興局と協議、災害復旧支援車両ステッカーを作成・会員企業に配布、野田村へランドセル・文房具等の物資提供依頼開始(久慈支部・久慈青年会議所)
(北上支部)緊急役員会(今後の支援体制について協議)
(一関支部)炊き出し実施(一関土木センター)、大船渡に重機搬入(復旧活動実施)
(遠野支部)復旧作業活動中の会員企業の建設機械および車両にタンクローリーで給油活動実施
(二戸支部)緊急役員会(災害対応協議)、会員に対し支援物資の要請(二戸事務局に集約)
- 3月15日
- (釜石支部)沿岸広域振興局と今後の対応・復旧作業について協議
(岩泉支部)岩泉土木センター・岩泉町・田野畑村の指示でダンプ調達、各管内の業者が復旧活動実施
.jpg)
.jpg)
(一関支部)炊き出し実施(国交省一関出張所)
(千厩支部)緊急役員会(今後の支援体制について協議)
(遠野支部)現地応急復旧活動実施、沿岸広域振興局土木部長から現況と今後の応急復旧作業について説明、沿岸広域振興局へ燃料確保状況及び釜石支部会員への提供可能状況について報告

(ガレキを撤去して通行が確保された大槌町内の道路)
- 3月16日
- (本部)内閣府副大臣から建設業協会の復旧対応状況確認および応援要請、会長が岩手県・岩手河川国道事務所へ今後の応急復旧対策について要請
(釜石支部)復旧活動中の作業員向けの炊き出し実施
(宮古支部)行政関係機関と協議、宮古地区災害復旧対策連絡協議会設置(建設業協会宮古支部・宮古建設協会・宮古電業協会・宮古市水道工事業協同組合・管工業協会宮古支部・宮古市指定下水道工事店・宮古建築組合・岩手県沿岸広域振興局・宮古市役所・宮古商工会議所)

(久慈支部)久慈市土木課と燃料確保について協議
(盛岡支部)緊急理事会(災害対応協議)
(一関支部)陸前高田市で災害復旧作業実施
_2.jpg)
_1.jpg)
_3.jpg)
(緊急車両の通行が可能に)
- 3月17日
- (本部)沿岸部へ支援物資搬送(食料品・飲料水等)
(大船渡支部)大船渡市対策本部(大船渡市総務部)と水沢支部三役とともに協議(今後の作業展開、がれき撤去・捜索活動、後方支援の見通し、被災した車・船・家屋等のがれきの仮置場確定後の応援要請)
(久慈支部)災害復旧支援本部設置、県北広域振興局土木部と震災対応について協議、県北広域振興局からの指示で道路・港内・河口堰等のがれき撤去・流木撤去作業実施
(水沢支部)支部三役が大船渡市災害対策本部・岩手県大船渡土木センター・岩手県建設業協会大船渡支部を訪問(市対策本部の大船渡市総務部と協議)、灯油100L・ペットボトル60本・マスク・食料等の物資を大船渡市対策本部へ搬入
- 3月18日
- (本部)岩手県・岩手河川国道事務所に、会員企業の資機材の保有状況に関する調査の結果を提供
(岩泉支部)支部役員会開催 今後の応急復旧対応について協議
(久慈支部)野田村役場災害復旧について協議、野田村4河川のがれき撤去および調査実施、災害復旧支援対策本部、緊急役員会開催
- 3月19日
- (宮古支部)宮古市の姉妹都市である青森県黒石市の黒石市建設業協会から支援物資搬入(トラック3台、軽油トレーラー)


(岩泉支部)岩泉土木センターに応急復旧対応打合・状況を報告
(久慈支部)久慈市から廃棄物集積においての注意点指導、民家家屋の撤去・県北広域振興局の指示で水門流木撤去・漁港がれき撤去作業、支援物資が野田村の建設業者へ

(花巻支部・北上支部)釜石土木センター並びに釜石支部訪問・情報収集(北上支部と合同)、釜石支部に支援物資搬入(ポール50本・灯油300リットル・軍手1箱・ゴム手30個・飲み物等)
.jpg)
.jpg)
- 3月20日
- (久慈支部)行政機関に対して支援物資提供
(遠野支部)釜石支部へ支援物資としてプロパンガス搬入、会員企業ボランティア活動開始(釜石・遠野間で大型バス運行支援、宿泊施設での入浴)

- 3月21日
- (本部)会長・専務 岩手県・岩手河川国道事務所へ要望書提出
(久慈支部)野田村と施工計画について協議、民間家屋のがれき撤去作業実施
- 3月22日
- (本部)岩手県・プレハブ建築協会と打合 仮設住宅の施工について協議
(岩泉支部)岩泉土木センターから河川等のがれき撤去の依頼
(千厩支部)自衛隊から岩手県経由で重機の派遣要請があり山田町へバックホウを3台派遣
(二戸支部)支援物資を本部へ搬送(毛布・おむつなど)
- 3月23日
- (本部)栃木県建設業協会、資材連合会からの支援物資を沿岸支部に送付(大船渡・釜石・宮古・岩泉・久慈)
.jpg)
.jpg)
(一関支部)一関支部、千厩支部合同役員会(沿岸地区への支援、災害復旧対応に関する協議)
(千厩支部)一関支部、千厩支部合同役員会(沿岸地区への支援、災害復旧対応に関する協議)、支部役員会(今後の支援体制、気仙沼市への給水支援について協議)
- 3月24日
- (本部)会長 宮古・釜石・大船渡の各支部・国・県訪問し、国・県・市に対し支援指導要請
.jpg)
.jpg)
(岩泉支部)岩泉・田野畑地区災害復旧連絡協議会設置(岩泉土木センター・岩泉町・田野畑村、建設業協会岩泉支部)、管内河川災害復旧・田野畑村海岸線沿いの県道がれき撤去作業開始
(久慈支部)野田村でがれき撤去作業実施、国道45号線復旧工事実施、久慈市に対して稼働可能重機調査結果を報告
- 3月25日
- (本部)正副会長会議(被災対応報告、資金・資材の確保、労働災害、支援活動等について討議)、会長が岩手県へ応急復旧に関する要請

(一関支部・千厩支部)被災地状況把握、大船渡支部長と会談、大船渡支部で管内の状況確認



(千厩支部)気仙沼市での給水活動(室根町業者が14日より実施中)に青年部会が人員支援を開始

- 3月28日
- (一関支部・千厩支部)一関支部・千厩支部合同で会員企業提供の毛布等を大船渡支部へタンクローリー1台分の経由(2000L)とドラム缶10本を支援物資として搬入


- 3月29日
- (本部)第4回理事会(沿岸各支部および遠野支部から現状報告、岩手県建築住宅課およびプレハブ建築協会より仮設住宅建設に関して説明)

(釜石支部)釜石・大槌地区災害対策本部を釜石支部会館に移動
(盛岡支部)日本赤十字社(岩手日報窓口)に義援金を贈呈
- 3月30日
- (本部)会長が岩泉・久慈の各支部・県・町に対し応急復旧の支援要請
(久慈支部)三役会議(応急復旧業務について)、県北広域振興局より支援物資「防塵マスク」支給
- 4月2日
- (大船渡支部)気仙地区災害復旧対策連絡協議会設置(三陸国道事務所大船渡出張所、沿岸広域振興局、大船渡市、住田町、陸前高田市、大船渡支部、陸前高田建設企業団、電業協会気仙支部、管工業組合、クレーン工業協会)
- 4月5日
- (本部)会長が岩手県・岩手河川国道事務所へ要望
.jpg)
.jpg)
(盛岡支部)宮古支部の要請を受けてがれき撤去のため重機・人員派遣、自衛隊の指揮下でがれき撤去・捜索活動開始(宮古市田老・鍬ヶ崎、山田町)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 4月11日
- (大船渡支部)大船渡市内全域でがれき撤去開始
- 4月14日
- (本部)正副会長会議 釜石支部・大船渡支部への支援内容協議
(釜石支部)釜石市内民有地のがれき撤去作業開始
- 4月19日
- (久慈支部)会員企業(主に青年部会)が野田村生涯学習センター等ボランティアで土砂撤去作業

- 4月21日
- (本部)会長団・専務が沿岸広域振興局等関係訪問(がれき撤去・仮設住宅等について意見交換)

- 4月25日
- (千厩支部)陸前高田市建設企業団からの要請を受けて陸前高田市でのがれき撤去作業開始
- 4月26日
- (遠野支部)遠野農林センターと合同で大槌町吉里吉里にて入浴施設を提供
.jpg)
.jpg)
- 5月11日
- (宮古支部)全壊・半壊家屋を含めた本格的なガレキ撤去作業開始

(千厩支部)陸前高田市へ一関市大東支所を通じて作業着を寄贈(被災者の片付け作業用、上着90着、ズボン50着)、支部長 陸前高田市で支部会員のガレキ撤去作業を視察・激励



- 震災から2ヵ月を迎えた5月11日、宮古湾で復興祈願の鯉のぼりが掲揚された。

- 5月17日
- (北上支部)沿岸被災者支援として北上市に義援金を贈呈
- 5月20日
- (北上支部)沿岸被災者支援として西和賀町に義援金を贈呈
(掲載写真の一部は日刊岩手建設工業新聞社から提供頂きました)
東日本大震災関連の最新情報(いわけんブログ)
各地の被災状況写真- 田野畑村
.jpg)
.jpg)
- 宮古市
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 宮古市田老地区
- 宮古市田老地区を津波が襲った瞬間、10mの防潮堤を超える。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 釜石市
.jpg)
.jpg)

- 大槌町
.jpg)
.jpg)
- 大船渡市
.jpg)
.jpg)
- 陸前高田市

.jpg)
.jpg)
.jpg)
陸前高田市では気仙川を津波が8km遡った。竹駒町付近に大量のガレキが運ばれてきた。
.jpg)
復旧作業、がれき撤去作業に関わる教訓- 現場で不足したもの
- 今回の震災では燃料不足(軽油やガソリン)が深刻な事態に陥った。
作業で必要な防塵マスク、作業用手袋、作業用ゴム手袋、軍手、タオル、ブルーシート、安全ベストが不足した。
ダンプなどの車両が釘などを踏みパンク、パンク修理が出来る場所がなかった。
重機が故障、重機の修理を出来る場所がなかった。
- 健康上の問題と対策
- 乾いた土砂などが風で舞い、粉塵が立ち込める→防塵マスク、ゴーグル
流された建材に紛れ込む石綿→防塵マスク、散水・薬液処理による湿潤化、建材を割らない
傷口から破傷風に感染の恐れ→丈夫な手袋、安全靴など底の厚い靴、長袖の作業着、傷を負った際の消毒・治療、予防接種
PCBの混在→古いトランス、コンデンサー等PCBを含むものを触らない
- 安全上の問題と対策
- 余震による津波の発生→ラジオで把握、避難経路の確保
作業員、第三者と作業用機械の接触→第三者の立ち入り禁止、作業半径内立ち入り禁止、誘導
被災した建物の倒壊→建物の状況・強度確認
重ねたガレキの倒壊→重ね過ぎない、ガレキ上で作業を避ける
釘の踏み抜き→安全靴など底の厚い靴
公共工事動向4月を更新しました
2011年5月 9日 16:28岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内4月版)を掲載しました。
↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)4月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
国・県へ要望書を提出
2011年4月 7日 19:06岩手県建設業協会
岩手県建設業協会では4月4日(月)岩手県と東北地方整備局岩手河川国道事務所に対して以下のとおり要望をしてきました。
被災された事業者は地域の復旧に努力しており、内陸部の会員においても復旧・復興に向けた万全な体制を整えているところですが、建設産業全体としては、工事中止や契約保留のため、資金繰りに窮している企業も少なくない状況にあり、沿岸地域においても、震災により多くの事業所が休業などを余儀なくされています。
このことから、地域にとって雇用機会の創出や確保が課題となっており、今回要望することとなりました。岩手県への要望
1 復旧活動に支障を生ずる恐れのない工事については、中止や契約保留の措置を緩和していただきたいこと。
2 被災した企業に対する運転資金・設備資金を手当するための制度資金の創設や拡充をお願いしたいこと。
3 復旧事業への地元建設業者等の優先的発注をお願いしたいこと。
4 復旧に係る資材の調達に当たっては、地元業者を参入させていただきたいこと。
5 金額や工事期間にかかわらず、全ての応急復旧工事を前金払(中間前金払)制度の対象にしていただきたいこと。
6 がれきの撤去作業の経費については、作業上の拘束及び待機の時間を勘案のうえ積算していただきたいこと。
7 工事一時中止期間については、工期延長をお願いしたいこと。
8 津波によって流失した建設機械及び自動車等については、契約上の不可抗力による損害扱いとして頂きたいこと。
9 被災にあった工事については、出来形確認を行い、部分払いで対応願いたいこと。
10 復旧活動に支障が生じない範囲での、震災に直接関係しない内陸部等における
工事の発注をお願いしたいこと。
岩手河川国道事務所への要望
1 復旧活動に支障を生ずる恐れのない工事については、中止や契約保留の措置を緩和していただきたいこと。
2 復旧事業への地元建設業者等の優先的発注をお願いしたいこと。
3 工事一時中止期間については、工期延長をお願いしたいこと。
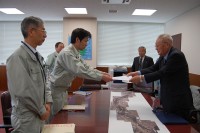
岩手河川国道事務所へ要望
岩手県へ要望
※写真は日刊岩手建設工業新聞社より提供頂きました。
公共工事動向3月を更新しました
2011年4月 4日 18:24岩手県建設業協会
(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。
「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内3月版)を掲載しました。
↓PDFファイル↓
公共工事動向(岩手県内)3月版→ こちら(PDF)
 ← クリックにご協力を
← クリックにご協力を
北の大地から救援物資が届きました!
2011年3月22日 12:42岩手県建設業協会

21日、東北地方整備局岩手河川国道事務所の仲介により、北海道建設業協会から東北地方太平洋沖地震の被災地に対する救援物資(軽油、灯油、トイレットペーパー、粉ミルクなど)がタンクローリーやトラックで届きました。被災地で災害復旧作業にあたる地元建設業への燃料も含まれています。
タンクローリーやトラックに会員企業の方々が直接乗り込み、岩手産業文化センターに集結しました。タンクローリーで現地にそのまま向かうという徹底ぶりに頭が下がります。
北海道建設業協会の方々に心より感謝申し上げます。思いは一つです。


≪情報・写真提供 東北地方整備局岩手河川国道事務所、日刊岩手建設工業新聞社(以下3月22日同紙紙面より)≫

東北地方太平洋沖地震からの復興に向け、自衛隊や消防などに協力しながら被災地での土砂とがれきの撤去に尽力する本県建設業界。そのような中、北海道建設業協会(岩田圭剛会長)からは、本県に対する救援物資として灯油や軽油などが送られた。21日には岩手産業文化センター(アピオ)にタンクローリーとトラックが到着。北の大地からの救援物資を積んだ車両が、沿岸部や盛岡市周辺の病院などに向かった。
支援物資の主なものは、軽油27・7キロリットル、灯油54・7キロリットル、ほかトイレットペーパーや粉ミルクなど生活支援物資6トン。今回の救援物資を提供したのは、札幌、空知、帯広、留萌、室蘭の5地区の会員企業で、取り引きをしている商社などから無償で提供を受けたもの。このうち軽油20キロリットルは、がれきなどの撤去に当たる地元建設企業の災害対応用として使用し、残りは各被災地に届けられる。
総勢24人の一行は20日朝に苫小牧港を出発。21日の午前には15台のタンクローリーとトラックがアピオに到着したほか、八幡平市と釜石市には1台ずつが直接向かった。
県土整備部の若林治男道路都市担当技監、仲介の窓口を務めた東北地方整備局岩手河川国道事務所の今日出人所長が一行を出迎え。各車両は若林技監からの指示を受けて、宮古市、釜石市、岩泉町、大槌町の沿岸部、盛岡市内周辺の病院などに向かった。若林技監は「被災されている住民の方も含め、大変感謝している。特にもタンクローリーで現地まで運んでいただけることは、非常にありがたい」と感謝の意を表す。
東北6県の建設業協会と北海道建協とは古くから交流があり、今回の救援物資の提供はその流れにあるもの。また北海道では官民上げて燃料や生活物資の支援を行っており、北海道建協からは東北建設業協会連合会に対する義援金も送られている。今回の支援隊の隊長を務める空知建設業協会の砂子邦弘副会長は「岩手の企業には知り合いも多く、北海道で働いている協力会社の中には岩手の人もいる。いまだかつて無い大災害で、日本そのものの危機とも言える状況であり、微々たる援助だが少しでも被災地のお役に立てれば」と話している。
「がんばろう!岩手」を表示しました。
2011年3月19日 16:08岩手県建設業協会
東日本大震災から1週間が経過した18日より、岩手県建設業協会の公式ホームページといわけんブログに「がんばろう!岩手」と表示しております。
復旧・復興に向けた支援の輪が広がりつつあります。
月別アーカイブ
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年